初めてメカニカルキーボードを使いました
低予算で打鍵感がいいキーボードを探す
仕事関係でiPadで使えるキーボードを購入することになりました。個人的にはHHKBがお勧めなのですが,予算的に厳しいため低予算で購入できるメカニカルキーボードをさがすことにしました。amazonで品物を物色しているとKeychron C3 Proが6,000円台で販売されているのが目に留まりました。KeychronブランドのキーボードはHHKBと同じ高級キーボードというイメージがあったのでちょっと意外な感じでした。75%キーボードなので少し大柄なのが気になりましたが,購入して使ってみることにしました。
WebでのレビューはJIS配列の製品のものが多いのですが,購入したのはUS配列のものです。
ファーストインプレッションは…
週末に注文して翌週には届きました。開封する前に箱を持ったときの印象は「重い」でした。その後開封したときの本体のファーストインプレッションは「大きい」でした。HHKBの60%キーボードに慣れているとかなり大きく感じます。プラスチック筐体で見た目軽そうな印象ですが,かなりずっしり感じる重さです。質感は安っぽい感じもなく,スペース,ENTER,ESCの3つのキートップが赤になっているのがいいアクセントです。(交換用の黒キートップも付属しています)
気になる打鍵感は…
iPadとWindowsPCに接続してタイ速などのタイピング練習サイトで試し打ちをしてみました。HHKB(私が使っているのはType-Sではないです)はキーを押しこむときはそれほど音がせず,指が離れるときに音が聞こえる感じなのですが,Keychronはキーを押し込むときに音が聞こえる感じです。全体的にはとても静かな印象でカタカタ…という感じの音です。この音が結構心地よく,打鍵感もいい感じにしている気がします。
iPadで使うときはMacモードが便利
Keychron C3 ProはMacモードとWindowsモードを切り替えることができ,iPadで使うときはMacモードにすると細かい設定をしなくても使うことができて便利です。
その他使ってみて感じたこと
(1)バックライトは赤1色
光らせ方のパターンはたくさんありますが,点灯するとキートップの文字が赤く光るのでいい感じです。気分で点灯/消灯を切り替えるのもありだと思います。
(2)Keychron Launcherウェブアプリでカスタマイズできる
まだ使っていませんが,キーマップをカスタマイズできるWebアプリが提供されています。低価格帯のキーボードでもカスタマイズ用の公式ツールが提供されているのはいいですね。WindowsPCで使うときはとりあえずHHKB用に作成したAutoHotKeyの設定を手直して使っています。スペースキーの両端がAltキーなのでAltキーで日本語入力切替ができるようにしています。
(3)ケーブルの取りまわしがしやすい
接続する機器にあわせて有線ケーブルを本体の左側面/右側面/上中央から出せるようになっています。地味に便利な機能です。
(4)トラックパッドまでが遠い
75%キーボードなので仕方がないことですが,トラックパッドを操作したいときに右手をかなり右に移動しないといけないのが気になりました。
(5)カーソルキーが遠い
独立したカーソルキーが右下にあるのですが,かなり遠くにある印象で使いにくいです。カスタマイズしてHHKBと同じようにFnキー併用に変更するといいかもと考えています。
(6)Backspaceキーを押し間違える
HHKBと異なり,Enterキーの上がBackspaceキーではありません。そのため頻繁に押し間違えます。(2)のAutoHotKey設定でEmacsキーバインドが使えるようにしているので,Ctrl+Hで代用しています。
(7)Aキーの左側がCtrlキーではない
HHKBと異なり,普通のメカニカルキーボードはAキーの左側はCapslockキーになっています。Ctrl2CapsというアプリでCapslockキーをCtrlキーに変更して使っています。
メカニカルキーボードもいいかも
今回Keychron C3 Proを使ってみて,大きさと重さ以外は好印象でした。これで60%キーボードだったらさらに高評価になっていた気がします。
個人的なお気に入りポイントは打鍵感で,HHKBとは違った感じですが入力しているときのカタカタ…という音が上品でよかったです。一番下のグレードでこの打鍵感なので,上位グレードのKeychronはもっといいのかも…と期待してしまいます。
メカニカルキーボードは種類も豊富で価格帯も様々なので選ぶ楽しみがありますね。更に軸を替えたり,自作キーボードがあるなど,カスタマイズの楽しみも大きいと感じました。反面,はまったら結構深そうな沼なので気をつけないといけないなと思いました。私ははまらないように静電容量無接点のHHKBを使い続けていきます。
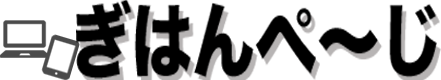













この記事へのコメント
コメントはまだありません。
コメントを送る